
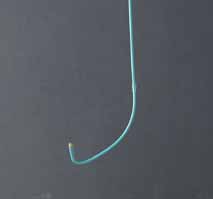
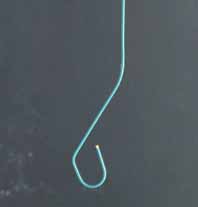
€ ジャドキンス・タイプ
TRIの手技では、ガイドカテーテル先端を冠動脈内にDeep engage(深く挿入してカテーテルと冠動脈との摩擦力によりカテのバックアップを取ろうとするテクニック)することが多いので、基本的には先端チップのフレキシブル度が問題になるでしょう。これが優れているガイドカテーテルは、最初に冠動脈に引っ掛かってくれてPTCAワイヤーさえ通すことができれば、そのワイヤーを利用してDeep engageが可能です。
そういう意味では、左冠動脈に一番エンゲージしやすいジャドキンスタイプで、先端がフレキシブルにDeep engageに対応しているタイプのガイドカテーテルが最もポピュラーなガイドカテと言えるでしょう。最近は各社ともTRIを意識した(Deep engageに対応している)ガイドカテーテルを製品化しています。
右冠動脈用のジャドキンスタイプはfemoral用と同じですが、TRIでも多く使用されているようです。
アンプラッツ・タイプ
大腿動脈アプローチ用に作られたアンプラッツタイプのカテーテルもTRIに使用できます。サイズも左冠動脈用はAL2、右冠動脈にはAL1.0, AR2などが合うようです。
¡ MUTA・タイプ
以下は帝京大学・落合正彦先生に執筆(2000年12月)していただきました。
MUTA カテーテル開発の経緯
私は、long-tipカテーテルを使い、大動脈の対側でしっかりバックアップをとってPTCAをするのが大好きです。これは是非をとやかく言うよりも、「この仔羊にはボルドーが合う、いやローヌの方が美味しい」と同じで、完全に趣味・嗜好の問題です。オートマチックの「D」にギアを入れて、思いっきりアクセルを踏んで車を運転する感覚です。
大腿動脈から、あの固いPalmaz-Schatz stentのdeliver systemを、8Frカテを使って植え込んでいた頃、Judkinsでは一向に進まないものの、ガイドカテをVodaに変えたとたんすっと入っていくのを随分と経験しました。また、術力にも問題が多かったのでしょうが、カテの挙動が一定しないAmplatzには泣かされたこともを少なくありませんでした。TRIを始めた96年当時、ステントは依然Palmaz-Schatzだけで、8Frになれた身としては、6Frカテは8Frと比べ遥かにバックアップが弱く感じられました。いかにbare
mountingでdelivery systemよりはましなものの、こんな細いカテでステントが入るのか、とても心配でした。私は、long-tipが好きなのと同じくらいAmplatzが嫌いなので、これは形状を工夫して、TRI用のlong-tipカテーテルを作っていくしかないと考えました。POBAでも、ステント植え込みでも、CTOでも、何でも、どんな患者でも使えるようにとの気持ちから、MUTA
(Multi-purpose Use in Trans-radial Approach) と命名しました。決して、東洋の神秘、あの「ザ・グレート・ムタ」からとったのではありません。
まず、左冠動脈用についてお話しましょう。TFIにおける最強のガイドカテはVoda Left
(VL) / Extra Back-up (EBU or XB)だろうと思います。会社によって呼称は違いますが本質的には同じもので、このカテーテルのコンセプトを述べたDr
Vodaの原著は、不朽の名論文です。Amplatz の欠点についても理論的に分かり易く解説されています。若い術者の皆さんには、是非一読をお勧めします(Voda
J. Cathet Cardiovasc Diagn 1992; 27: 234-242)。TRIを始めたばかりの頃は、技量未熟のため、VLやEBUを挿入できないことがしばしばありました。その理由は、右TRIでは、時に、左冠動脈の対側にこのカテの接地点を誘導しにくいことが上げられます。高血圧歴が長く上行大動脈が俗に「寝て」いたり、高齢で腕頭動脈の屈曲が強い患者さんでは特にそうです。そんな時に出会ったのが、現在三井記念病院で活躍されている伊苅先生が試作された、右上腕動脈アプローチ用Judkinsカテーテルでした
(Ikari Y, Ochiai M, Hangaishi M et al. Cathet Cardiovasc Diagn
1998; 44: 244-247) 。カテの途中を大きく曲げることで、接地点を自動的に、左冠動脈の対側に持ってこようというものです。このコンセプトに、long-tipの先端を組み合わせて左冠動脈用MUTA
カテーテルが完成しました (Ochiai M, Iakri Y, Yamaguchi T et al. Cathet Cardiovasc
Intervent 2000; 49: 218-224) 。
メリットは、まず、極めて入れやすいことです。ワイヤ先導でカテを下ろしていけば先端は自然に左Valsalva洞に入りますので、後はサイズの選択さえ間違っていなければ、ワイヤを抜いてカテを引き上げるだけで左冠動脈に挿入できます。時々、多くは時計方向に、少しまわしてやらないといけないこともあります。LAO
45。で操作するのが最も簡単で、カテが真横に向けば大体入ります。
現在では、正直に申しまして、内腔の関係から、私のカテラボでも一番多く使うのは、通常、メドトロニックのZuma 2 EBUです(EBUの入れ方のコツは後で述べます)。左冠動脈用MUTAカテーテルの最もよい出番は、腕頭動脈に強い屈曲があったり、通常の位置に比べ左側から上行大動脈に入ってくるようなケースです。EBUに比べ遥かに簡単に入ります。入ってしまえば、バックアップはEBUと同等ですし、バルーンをアンカーに使えばdeep
engageも容易です。ボストンが頑張って、0.070 inchの内腔のものさえ作ってくれれば、今でも第一選択のlong-tipカテーテルであると確信しています。
欠点ですが、これを裏返すことになりますが、ボストンの現在のシャフトにあります。まずZuma 2に比べて細いことです。また、Wise
guideのversionは、カテの固さに変化をつけていることが特色ですが、これが逆に仇になって、先端から2番目のsegmentの所で容易に、曲がったり、ちょっと長い間使っているとタレてしまい、私の大嫌いなAmplatzに類似した入り方になってしまいます。0.064
inchでも、0.066 inch でもインターベンションのstrategyは同じです。kissing inflationができるわけでも、1.75
mm のロータができるわけでもありません。今でも私は原則Cyberのものを使用しています。long-tipカテーテルの特性として、Judkins以上にサイジングに気を配る必要があるのも欠点といえば欠点でしょうか?
Judkinsでしたら、大体JL 3.5でおおよその用が足りますが、MUTAは、3.5にするか4.0にするか、慣れがいります。ちなみに、名前はML3.0-3.5-4.0-4.5となっていますが、実際はtipの長さは3
mm刻みです(そういえば、最近EBU 3.75が出ましたっけ)。
次に、右冠動脈用ですが、入れやすく、なおかつバックアップの強いデザインは考えつきませんでした。右MUTAは入れるのに熟練を要する代わりに、思いっきり強いバックアップがとれるようにしてあります。このため、long-tip
のデザインに加え、立体成形を施し、対側大動脈壁にしっかりくっつくだけでなく、真にcoaxialな挿入が可能なようにしています。Heavy
dutyなカテです(Ochiai M, Iakri Y, Yamaguchi T et al. Cathet Cardiovasc
Intervent 2000; 49: 218-224)。
入れるのにはコツが要ります。まず、腕頭動脈起枝部のあたりまで、ワイヤを必ず入れてカテを操作します。カテのキンクを防ぐためです。LAO45。で操作しますが、カテの先端は通常左Valsalva洞にありますので、少し引き上げながらゆっくりと時計方向に回転します。カテが右Valsalva洞に入るや否や右冠動脈に入ることもありますし、その後押したり・引いたりの操作が必要なこともあります。右冠動脈用MUTAカテーテルのshaftは、絶対にCyberをお勧めします。Wise
guideは先端が曲がってしまいやすく、極めて扱いにくい印象があります。サイズは9割がたMR2.0でOKです。残り1割弱でしょうか、上行大動脈が極めて太かったり、右冠動脈の肩上がりの部分が長い患者さんではMR3.0を選びます。
Palmaz-Schatzの時代と比べ、今はステントが良くなりましたので、私もこのカテーテルを取り出すのは、いわゆるSchepherdユs
Crookと呼ばれる、右肩上がりで屈曲の強い症例です。バックアップがいいので、ワイヤを通すのも楽です(JRでは、ワイヤ操作中にカテが落ちることを皆さん経験されていると思います)。このカテも、バルーンをアンカーとして使えばdeep
engagementは簡単です。手前味噌になりますが、12月初め、“CIVIC”という小規模なPTCAのビデオカンファランスを、各メーカーさんの協賛も得て、東京で開きましたが、その会場で販売したビデオに典型例が出ています。興味のある方は、仲の良いメーカーさんに問い合わせてみてください。何とかしてくれると思います。現在、普通の症例には、内腔が大きく、バックアップがそこそこあり、それなりに入れやすいlong-tipカテーテルである、Zuma
2 MACないしChampを選んでいます。また、右冠動脈近位部に病変があり、long-tipカテーテルを入れたくないケースでは、上行大動脈にあるカテシャフトと右冠動脈近位部の間の角度は、右TRIの方が、TFIに比べ鋭角であることを考え、JRの代わりに内胸動脈用(IM)を使うと、意外に良い固定が得られます。IMはメーカーによってデザインがかなり異なるので、数社のものを置いておくと良いでしょう。
おまけ:経験的に身に付けた「左冠動脈にEBUを入れる」コツ
LAO45。で操作します。まず、ワイヤ先端を左Valsalva洞に誘導します。時計方向回転が必要な場合もあります。この段階でワイヤを腕頭動脈起枝部のあたりまで抜き、カテを造影剤で充填します。カテ先が左Valsalva洞にあることを確認します。上行大動脈がストレートなケースでは、カテを軽く引いてやると左冠動脈に入ります。これがうまくいかない場合、ないし最初から上行大動脈が寝ていることがわかっているときは、カテを時計方向に回転させながら、左Valsalva洞にゆっくり押し付けていきます。テストショットで左冠動脈入口部の位置を確認し、さらに時計方向にゆっくりと回し、押す操作を続けていると入ります。カテが深く入るのを避けるため、入る瞬間にちょっと引くのも大切です。そう、これはSones
(Multipurpose) カテの操作と同じなんです。これでも入らなければ、カテが左冠動脈入口部付近に来たとき、わずかに今度は反時計方向に回し、引き上げます。以上、慣れれば、90%位の症例でEBUが使えます。なお、サイズ的に大きすぎるEBUは、LMTを損傷する可能性があるので、慣れるまでは少し小さめで始めると良いでしょう。普通は、女性はEBU3.5、男性は4.0ないし3.75が目安です。LAO45。での、Judkinsの入りかたが重要です。経験をつめば、意外に体格が参考になることがわかります。
 |
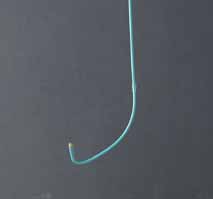 |
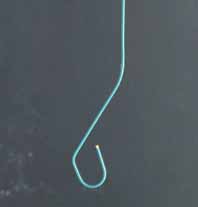 |
|
¤ Kimney・タイプ
(管理人にはほとんど使用経験がありません。使用経験が豊富な先生の投稿をお待ちしています。